「足場屋って鳶職のこと?」「鳶職っていろいろあるけど、何が違うの?」——現場経験がない方からよく聞かれるこの疑問。たしかにどちらも高所での作業を行う職業であり、外から見れば似たように映るかもしれません。でも、実際には仕事内容も求められる技術も、明確に違いがあります。
まず「足場屋」は、建設現場で作業員が安全に動けるように仮設の足場を組む専門業者です。建物そのものを作るのではなく、工事がスムーズに進むための「土台」をつくる裏方的な役割です。一方で「鳶職(とびしょく)」は、足場作業も含めつつ、鉄骨の建て方や重量物の据え付けなど、より広い範囲の高所作業を担当します。つまり、足場屋は鳶職の中でも特化型とも言える立ち位置です。
この違いを知らずに現場に入ると、「聞いていた仕事と違う…」と戸惑うことも少なくありません。これから建設業界を目指す方にとって、この違いをしっかり押さえることは、納得のいくキャリア選びの第一歩になります。次のセクションでは、現場で実際にどう呼ばれているのか、混同されがちな背景を掘り下げていきます。
現場ではどう呼ばれている?混同される理由とその背景
実際の建設現場では、「足場屋さん」「鳶さん」「とび職人」など、現場ごとにさまざまな呼び方が使われています。たとえば、足場の組立をしている人を「鳶さん」と呼ぶケースもあれば、「足場屋さん」と区別して呼ぶ現場もある。つまり、使い分けは職種の厳密な違いというより、現場の慣習や会社の文化に左右されているのが実情です。
この混同を生む大きな理由のひとつが、「鳶職」という言葉の広さです。鳶職には「足場鳶」「鉄骨鳶」「重量鳶」「橋梁鳶」などの分類があり、それぞれが異なる専門作業を担っています。中でも足場鳶は、足場専門の作業を行うため、一般的には「足場屋」とも呼ばれます。ただ、足場鳶が鉄骨工事や重量物据え付けを担当することはほとんどなく、それらは別の鳶職人が担います。
もう一つの要因は、元請けや現場監督が必ずしも専門職名を正確に使っていないことです。たとえば「鳶さんに声かけて」と言われても、それが足場屋のことなのか、鉄骨鳶のことなのかは、現場をよく知らないと判断がつきにくい。さらに、請け負う会社側も「鳶工事一式」として足場作業を請けるケースが多く、書類上でもあいまいになりやすいのが現状です。
こうした背景から、未経験者が最初に混乱するのは無理もないことです。特に求人票や面接で「鳶職募集」と書かれていたとしても、その中身が足場専門なのか、鉄骨作業を含むのか、はっきりとはわからない場合もある。だからこそ、自分がやりたい仕事がどの分類にあたるのかを事前に知っておくことが、ミスマッチを防ぐためには欠かせません。
仕事内容の違いと共通点―求められる技術と責任の幅
足場屋と鳶職では、扱う資材や作業の進め方、責任の範囲に明確な違いがあります。足場屋の主な仕事は、建物の外周や内部に仮設の足場を組み、現場の職人が安全に作業できる環境を整えること。組立から解体までが一連の業務となり、スピードと正確性、安全性が何より求められます。特に限られた工期内で作業を終える必要があるため、チームワークと段取りの良さが大きく影響します。
一方で、鳶職はさらに広範囲の高所作業に対応します。鉄骨をクレーンで吊り上げて組み上げたり、重量物を安全に所定位置へ据え付けたりと、建物の構造そのものをつくる作業に関わるのが特徴です。精密な位置合わせ、高所での資材取り扱い、合図動作など、緊張感の高い現場も多く、熟練した技術が不可欠です。
ただし共通しているのは、「落ちれば命に関わる」という高所作業である点。命綱の着用、声かけ、安全確認といった基本的な行動が、日常的に求められます。どちらの職種も、資材や工具の落下による第三者への危険もあるため、自分だけでなく周囲の安全にまで気を配れるかどうかが問われる仕事です。
また、どちらも体力勝負というイメージを持たれがちですが、実際はそれだけでは続きません。図面の読み取り、作業の段取り、機材の選定など、頭を使う場面も多いです。特に足場屋では、限られたスペースや建物の形状に合わせて足場を組む柔軟な発想力が必要ですし、鳶職では構造物の力のかかり方を理解する知識も重要になります。
つまり、両者の仕事内容は重なる部分もありますが、それぞれに特化した技術や責任があるというのが実態です。安易に「どっちも似たようなもの」と思わず、自分に合った道を見つけるためには、こうした違いをきちんと押さえておくことが大切です。
必要な資格・キャリアパスはどう違う?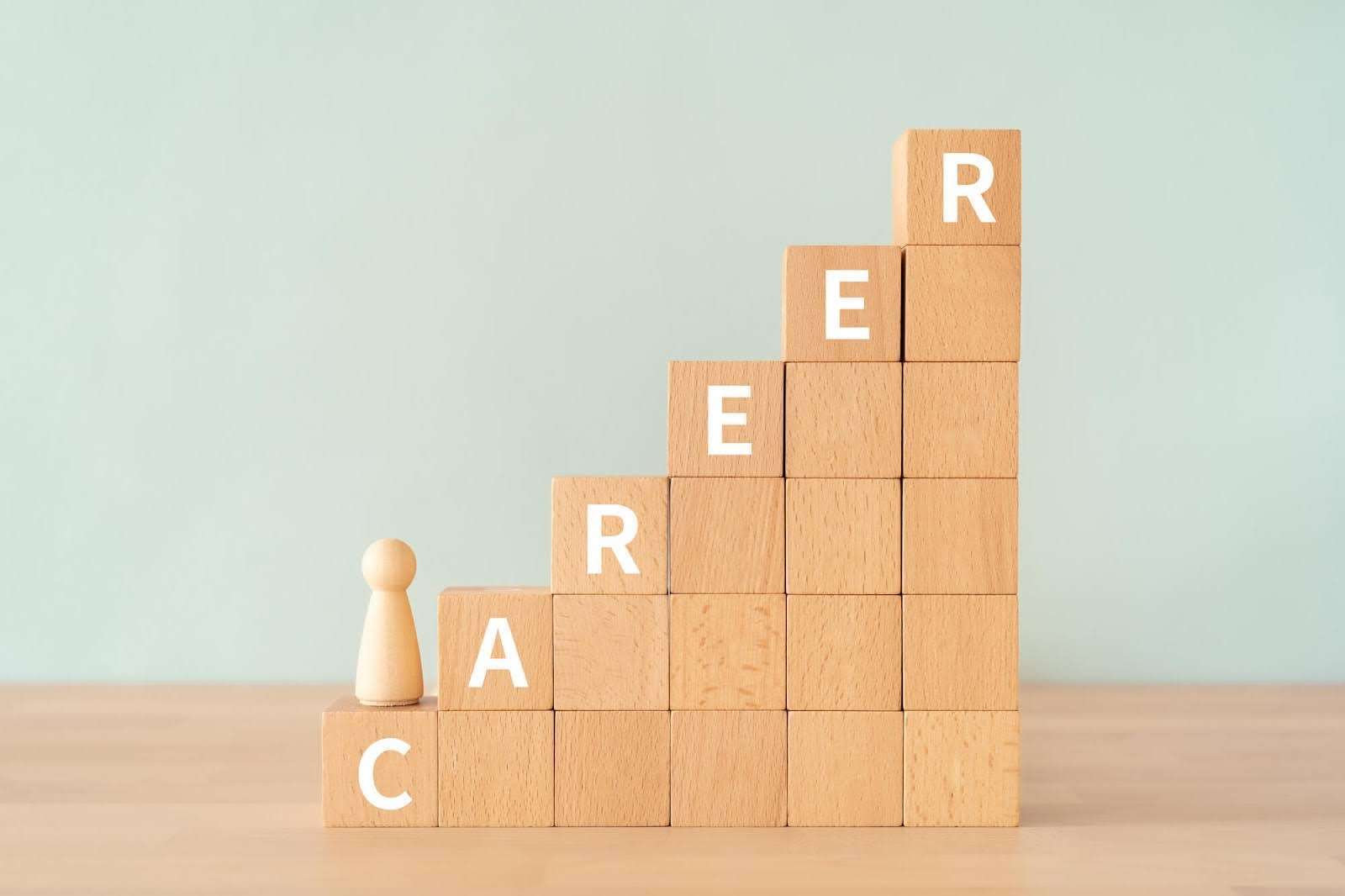
足場屋と鳶職、それぞれの仕事には、現場で求められる資格や経験の積み方にも違いがあります。まず、足場屋に関して言えば、未経験からでも始めやすい職種の一つです。とはいえ、現場で足場の組立てや解体に関わるには「足場の組立て等作業従事者特別教育」の修了が必要です。さらに、高所作業を安全に行うための「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」も現在では必須になっています。
経験を積んでいけば、作業主任者として現場を指導する立場になるために「足場の組立て等作業主任者技能講習」を受講することも視野に入ります。この資格があると、より大きな現場や責任あるポジションを任されるようになり、収入アップにもつながります。
一方の鳶職は、より幅広い作業を扱う分、資格のバリエーションも多くなります。たとえば、鉄骨鳶であれば「玉掛け技能講習」「高所作業車運転技能講習」「クレーン運転士免許」などが求められる場合もあります。また、「とび技能士(国家資格)」は職人としての技術を証明する資格で、1級・2級と段階があり、キャリアアップの指標になります。
キャリアパスの違いにも触れておくと、足場屋は職長として現場の段取りや安全管理を担う立場へ進むのが一般的で、そこからは独立して自分の会社を持つというルートもあります。鳶職も同様に、特定の分野(鉄骨、重量物、橋梁など)で経験を積みながら職長や施工管理者としての道が開けていきます。
どちらにしても、最初の一歩は「見て覚える」よりも「安全教育を受けてから始める」が主流になりつつあります。現場で信頼を得ていくには、資格を取ること自体よりも、それをきちんと活かせるかどうかが問われるという意識が重要です。資格はキャリアの“入り口”であり、その後どう積み重ねるかが将来を左右します。
未経験から始めるならどっち?向き不向きを見極める視点
足場屋と鳶職、どちらも現場で活躍できる仕事ですが、未経験から入る場合には「自分にどちらが合っているか」を事前に見極めておくと、入社後のギャップが少なくなります。最も大きな違いは、仕事の範囲と「扱うものの重さと高さ」。足場屋は仮設資材を反復して組む作業が中心で、ルールに沿った繰り返しの中で手際の良さと判断力を磨くことが求められます。一方、鳶職のほうが現場ごとの作業が多様で、技術の応用や場面ごとの対応力が必要になります。
また、体力だけでなく「空間把握力」や「高所での冷静さ」も重要な素養です。高い場所での作業が苦手であれば、どちらも厳しいのは事実ですが、とくに鳶職では鉄骨の上での作業や、重量物の移動に関わる場面もあるため、より神経を使う場面が多いといえます。反対に、足場屋は一定の型がある作業が中心になるため、「決まったことを正確にこなすのが得意」という人には向いている仕事です。
もうひとつ見逃せないのが、現場のチーム文化です。足場屋は比較的少人数のチームで動くことが多く、先輩との距離が近くなりがち。鳶職も同様ですが、より職人技が重視される場面では「見て覚える」文化が根強いこともあるので、どの現場に入るかによっても肌に合う・合わないは分かれてきます。
いずれにしても、実際に現場を経験しないとわからないことも多いので、最初から一つに決めつけすぎず、柔軟に考えてよい分野です。大事なのは「どちらが楽そうか」ではなく、「どちらの働き方に自分が長く耐えられるか」。その判断のために、見学や短期体験をしてみるのも非常に有効です。
今、足場ステップでは未経験からスタートできる現場職人を募集中です。現場のリアルを知りたい方は、ぜひこちらもご覧ください。
▶︎ https://www.asta-step.com/recruit
道を決めるのは、自分の目で「現場」を見ることから
足場屋と鳶職の違いを頭で理解しても、実際に働くイメージが湧かなければ、自分に合うかどうかは判断しづらいものです。大切なのは、「なんとなく」で選ぶのではなく、自分の性格や体力、将来の展望を踏まえて選ぶこと。そして、迷ったときには一度現場に足を運んで、自分の目で仕事の様子を見てみることが、一番の近道になります。
どちらの道にも、きちんと努力すれば成長できる環境があります。ただし、「向き・不向き」は必ず存在します。無理をして続けるよりも、自分にとっての“自然な選択”を見つけることが、長く働くためのコツです。焦らず、少しずつでいいので、現場の声や実際の動きを知っていきましょう。
▶︎ ご相談・お問い合わせはこちら:https://www.asta-step.com/contact


